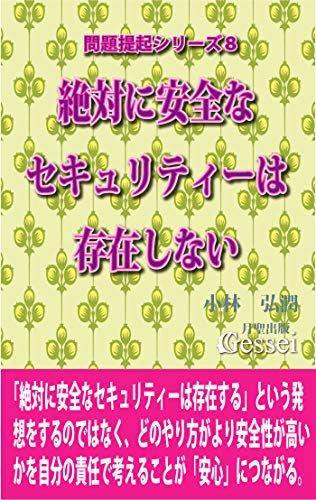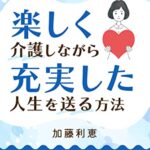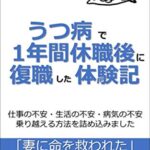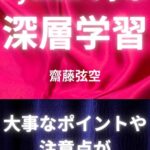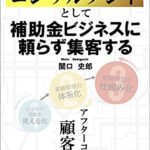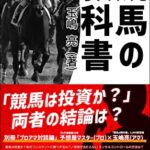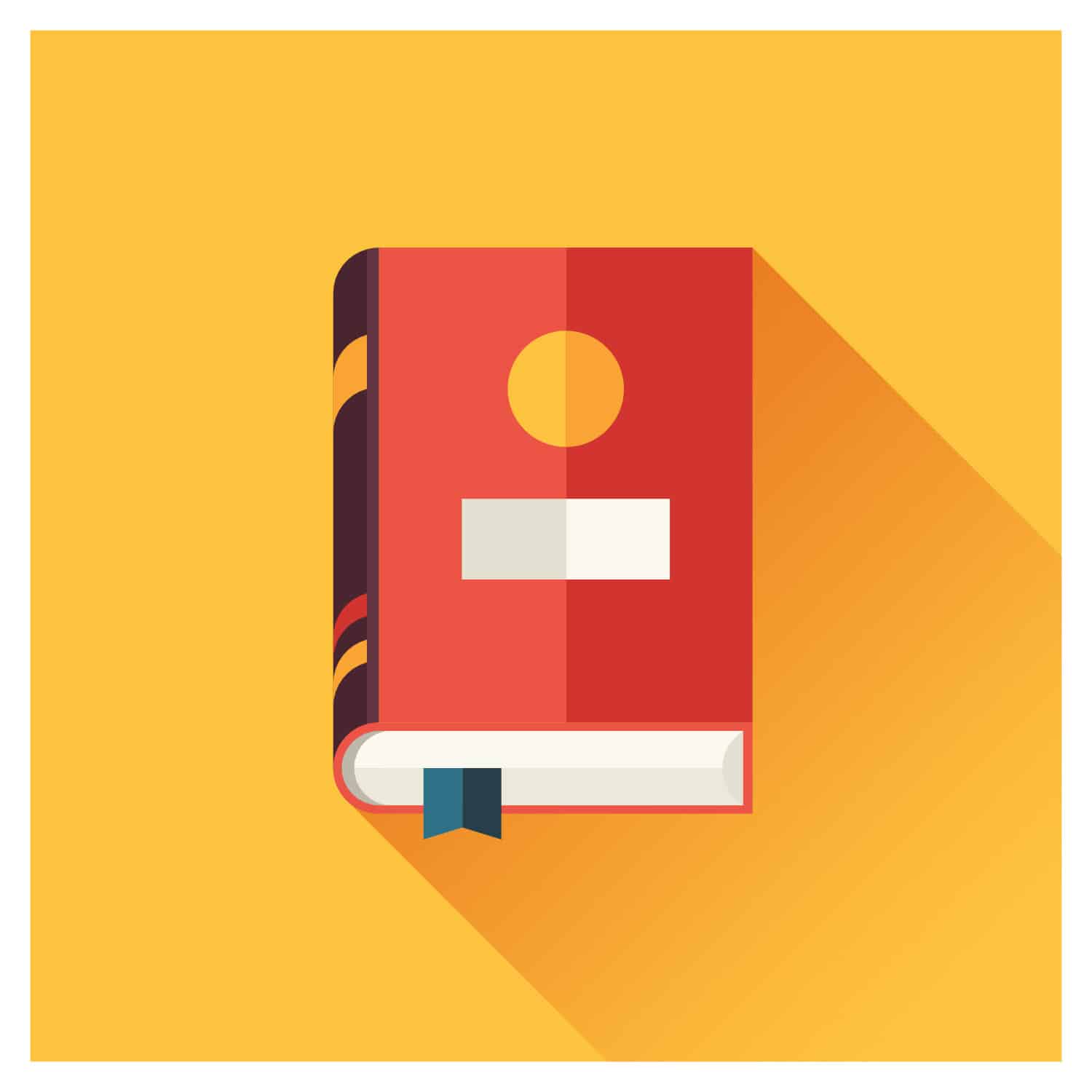著者:小林弘潤
ページ数:126
¥100 → ¥0
このことは、2019年7月に問題になった「セブンペイ不正利用問題」と比較すればわかると思います。セブンペイ問題とは「セブン&アイ・ホールディングスという一企業の不祥事」であり、被害者もセブンペイ利用者のみなので「セブンペイというキャッシュレス決済の問題」(キャッシュレス決済をやっていない人には一切関係がない問題)と言えます。それに対してドコモ口座問題の被害者とは「ドコモ口座を持っていない人々」(ドコモ口座と提携した銀行口座を持っている人全員が被害に遭う恐れがある)であり、「キャッシュレス決済はセキュリティー上危険と判断してやっていなかった人」であっても被害に遭っているからです。
「キャッシュレス決済は危険だと判断した人が、銀行に口座を持っているだけで被害に遭った」ということは「銀行に口座を持つことさえ危険だ」という意識になることを意味するので、そうした人々が「銀行などの金融機関にお金を預けることそのものが信用できない。これからは大事なお金は(タンス預金などで)自分自身で守るしかない」という思いになることは当然の結果だと思います。だからこそこの問題は「金融サービス全体の信用に関わる大問題だ」と断言できるのです。
やがてドコモだけでなく、様々なキャッシュレス決済業者や銀行や証券会社においても同様の不正引き出しが発覚したことで(ペイペイ、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、SBI証券等)〝底なし〟の様相を呈してきたと言えますが、個人的に「これは相当深刻だ」という気持ちになったのは、それまで「本人確認の認証方法としては信用できる」と言われてきたやり方(身分証明書の提示による本人確認やSMS認証等)が突破されたという話に接した時です。
例えば、9月16日に発覚したSBI証券の事件の場合、顧客6人から計9864万円が不正に引き出されたようですが、この事件では「保険証などの本人確認書類が偽造されて偽の口座を作られた」という話です(あと「ドコモ口座問題と比べて1人あたりの被害額が2ケタ違う」ことも深刻で、この事件に対しては「これって史上最悪レベルの恐ろしい事態じゃない?」とか「もう何も信じられない状況だ。本当に恐ろしい!」という声さえ出ていたもの)。
こうした不正引き出し事件が続々発覚する状況に対し、「もうキャッシュレス決済は信用できない」とか「ネットバンキングは危険だ」とか「デジタルよりアナログの方が安全だ」という声だけでなく、「銀行にお金を預けることさえも安心できない」「これからはタンス預金だ」という声さえ出てきたところがありますが(テレ朝の玉川徹氏はモーニングショーでこの問題を特集していた際、「自給自足だな」という言い方をしていたもの)、これらの事件は「(特にキャッシュレス決済やネットバンクをやっていない人の場合)自分には関係ないと誤解されやすい」ことでまだ世間の認知度は低く、「本格的なパニックが起こるのはこれからかもしれない」という思いになってしまうこともあります。
大事なことは、「もう何も信じられない!」というショックで疑心暗鬼になったりパニックを起こすのではなく、「どうすれば自分の資産を守れるかについて納得の行くまで考えるいい機会だ」という気持ちになって徹底的に考えてみることだと思います。
その際に必要な発想は「世間の一方的な意見を鵜呑みにするのではなく、様々な意見を比較検討しながら自分の頭で考えること」と「絶対に安全なやり方(セキュリティー)は存在しないという立場に立つこと」だと思います。例えば、「ネットバンクを信用できない」と主張しているある識者は金融機関に対して「ネットバンクの安全性を保証してほしい」という言い方もしているのですが、私にはこの人が「アナログは善でデジタルは悪という単純な思考パターンにはまっている」だけでなく、「絶対に安全なやり方は存在する」(だから金融機関はそうした完璧なセキュリティーを構築して我々を安心させる義務がある)という発想をしているように見えたものです。
こうした発想をする人の場合、「いつまで経っても不安や苦しみが続いて安心立命の境地に達しない」という感じがしてしまうのですが、大事なことは「ネットバンクや銀行やタンス預金などのメリットとデメリットを比較検討し、どのやり方がより安全性が高いかを自分の責任において考えること」だと思います。
私自身も考えた結果、「このやり方なら万が一犯罪者の侵入を許しても被害は最小限で済むから納得できる」という結論に達したところがあり、納得できてしまえばそれまであった不安や恐怖がなくなって安心立命の境地に達したものです。もちろん、結論は各人違っていいと思いますが、何らかの参考になればと思った次第です(ただ、金融やITに関しては素人なので専門的な話はできないことを最初に断っておきたい)。
まえがき ~深刻な不正引き出し問題に対して「もう何も信じられない!」と疑心暗鬼になるのではなく、納得行くまで徹底的に考えることが大事
1 ドコモの問題を聞いた多くの人が「ドコモ口座を持っていない自分には関係ない」と誤解してしまうことだけで、今までの金融犯罪とは違ったタチの悪さがある
2 個人的にこの問題が深く理解できたのはネットの声に接したからだが、その後「ネットの声とマスコミ報道があまりに違う」と思うようになった
3 ドコモの副社長は会見で「再開」という言い方をしていたが、ドコモの「サービスを停止しない判断」に憤慨している人々は「再開」なんて絶対に許さない
4 問題の重要性や深刻さと比較すると信じられないほど報道が少ないため、情報をテレビや新聞に頼っている人にはこの問題の実態はまるで伝わっていない
5 ドコモが9月14日の時点で「口座自体を止めることは考えていない」と言った時は「長年続けて来たドコモの携帯を解約するしかない」という気持ちになった
6 最初に会見したのがゆうちょだったらゆうちょに批判が殺到していた可能性がある以上、「ドコモは早めに会見したことで貧乏クジを引いた」とさえ言える
7 「会見さえしていない企業もある」という現実を考えると、最初に会見しただけでなく「全額補償の流れを作ったドコモ」を一方的に断罪するのはフェアではない
8 今回の私自身の「ドコモに対する認識の変化」は「情報が追加されたことで世界観が広がった事例」として考えることもできる
9 問題の根源は「決済業者や銀行を監督する政府や政治家の意識の低さ」にあり、「ITに疎い高齢者を担当大臣に就けているシステム」を考え直す必要がある
10 どんなに気をつけてもフィッシング詐欺に引っかかる可能性は拭えない以上、「どうすれば自分の資産を守れるかに関する対策」まで考えておく必要がある
11 「絶対に安全なやり方は存在しない」という立場に立ち、様々なやり方を比較検討して「より安全性が高いやり方」を自分の責任において考えることが大事
12 当初はタンス預金の選択肢も考えたが、検討してみると「補償の問題や限度額の問題から、想像以上にデメリットが大きい」という気持ちになった
13 狡猾で悪質な犯罪者であっても「既に定められた人間の行動原理という枠内で動いているだけの存在」でしかない
もう一つ、こうした発想をする玉川氏が「現金に絶対の信頼を置いている」ことも興味深いので注目してもらえればと思います。
これはお金の歴史を見てみれば一目瞭然ですが、昔は「現金であっても(今のキャッシュレス決済やネットバンクと同様に)信頼されていなかった」と言えるので(特に「紙幣」というものは、そのもの自体にはまったく価値がないことで流通が始まった当初は「私自身は紙幣を信用できないでいる」とか「紙幣は恐ろしくて持てない状態というのは、決して杞憂ではない」などと言っている人も少なくなかったと思う)、個人的には「キャッシュレス決済やネットバンクであっても、長い時間をかければ絶対の信頼が置かれるようになるんじゃないかな」という思いになります。
~「11 「絶対に安全なやり方は存在しない」という立場に立ち、様々なやり方を比較検討して「より安全性が高いやり方」を自分の責任において考えることが大事」より
先に紹介しましたネットの意見の中に「超低金利だから銀行に預かるメリットが浮かばない」という声がありますが、私はこれとは違った意見を持っています。というのも、「銀行に預けるメリットがない以上はタンス預金にする」という道を選んだ場合、完全な自己責任になるので「財産を失っても一切補償されない」と言えるからです。
もちろん銀行やネットバンクに預けた場合でも「利用者側のミスや過失で財産を失った場合は補償されない」と言えますが、それでも「(ドコモ口座問題における全額補償の方針のように)金融機関側の問題と認定されれば補償される」ことを考えますと、「完全な自己責任になるタンス預金よりは安心できる」(補償されることによる安心感というメリットはある)と言えるのではないかと思います。
~「12 当初はタンス預金の選択肢も考えたが、検討してみると「補償の問題や限度額の問題から、想像以上にデメリットが大きい」という気持ちになった」より
シリーズ一覧
- 同シリーズの電子書籍はありませんでした。
この期間中は料金が980円→0円となるため、この記事で紹介している電子書籍は、すべてこのKindle Unlimited無料体験で読むことが可能です。