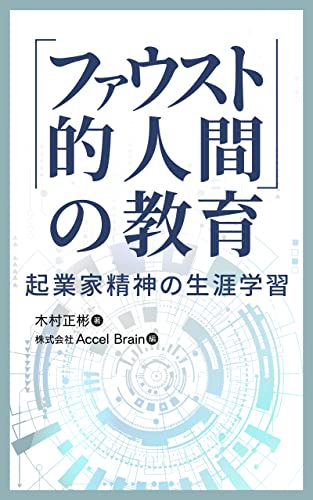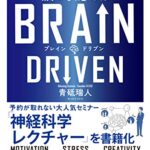著者:木村正彬
ページ数:564
¥1,250 → ¥0
哲学をビジネスにしている人々の間では、「実力も運のうち」というキャッチコピーが流行している。元々これは主に「能力主義(meritocracy)」に対する批判的な検討のために導入されたキャッチコピーであった。しかしこのキャッチコピーは、今では「格差社会」や「資本主義」に対する「批判的な」意識を先鋭化させるための「興奮剤」のようなものとして応用されている。
実際、成功体験を「実力」ではなく「運」に帰属させる発想は、成功体験を持たない者たちには都合の良い分析を可能にする。例えば、「あいつは運が良かった」という分析は、他人の実績や歴史を軽んじる者の嫉妬心を満足させる。一方、「自分は運が悪かった」という分析は、自身の選択や意思決定に伴うリスクの分析や責任を軽んじる者の保身を可能にする。「実力も運のうち」というビジネス哲学のキャッチコピーは、「他人に厳しく自分に甘い人間」には好都合な屁理屈としても応用できる訳だ。
しかし、この「実力も運のうち」というキャッチコピーは、決して万能ではない。この「他人に厳しく自分に甘い人間」が見落としてしまっているのは、「環境」のお陰で成功した場合であれ、「環境」のせいで失敗した場合であれ、自分自身もまたその「環境」それ自体の内部に包含されているという点である。
室内のインテリアや庭の花壇のように、我々はしばしば自分自身が設計した「環境」の中に自分自身を位置付けている。成功した原因にせよ、失敗した原因にせよ、その原因が「環境」にあるとするのなら、その<原因の原因>は自分自身にあるかもしれない。論理学的に言えば、<原因の原因の…原因>を遡ろうとすれば、無限に後退していくことになる。
このことの帰結として言えるのは、「自責」と「他責」の区別を導入することが、実は極めて困難であるということだ。全ての成功を自分の「実力」に帰責する成功者たちにせよ、あらゆる失敗を「運」の悪さに帰責する失敗者たちにせよ、この無限後退という問題を度外視している点では共通している。
ここまでの簡単な記述を踏まえれば、「実力も運のうち」というキャッチコピーは、「他人に厳しく自分に甘い人間」には好都合な屁理屈として機能するものの、最終的には堂々巡りの問題を生み出してしまうことがわかる。真実は、時折「自責」が機能し、時折「他責」が機能するというだけのことである。しかし、まだ人生や社会に絶望しておらず、これから成功を目指し挑戦しようとする者にとっては、あらゆる<原因>を「環境」に帰責する「他責」的な志向は役に立たない場合がある。
確率論的に考えれば、上述した屁理屈には更なる盲点がある。それは、目的達成の成功確率を歪みのない「一様分布(Uniform distribution)」として仮定してしまうという盲点だ。要するに、この屁理屈を鵜呑みにする人々にとっては、「成功する確率」と「失敗する確率」が等しく50%であるということになってしまう。それは、人生の成否が「全く歪みの無い硬貨」を使用したコイントスだけで確定すると妄想するあまりに、現実に存在する硬貨に歪みがある可能性を度外視することに等しい。
成功要因を「環境」に帰責する「他責」的な発想を自明視すると、他者の成功体験から学習する可能性が喪われることになる。例えば「裁定取引(Arbitrage)」を実践している投資家たちや「ブルーオーシャン戦略」を実践している起業家たちは、市場という自身に有利な「環境」を選択することで、勝利し続け、生存し続ける可能性を高めている。これに対し、成功確率を歪みなき一様分布として捉えた場合、自身に有利な「環境」を探索するという発想を、そもそも抱くことすらできない。結果、現にそれを実践している意思決定者たちの事例から学ぶことができなくなる。
この意味で、「実力も運のうち」というキャッチコピーは、「興奮剤」ではあるものの、使い方次第では、劇薬にもなる。特に、このキャッチコピーを「他人に厳しく自分に甘い人間」が屁理屈として利用した場合は、劇薬になってしまう。屁理屈と化したこのキャッチコピーには、成功体験を持たない者から学習する機会や動機を奪い去ることにより、「失敗者を失敗者のままにしておく機能」が備わっている。
哲学をビジネスにしている人々は、このことを認知しないであろう。何故なら、その方が都合が良いためである。
確かにこの屁理屈を並べておけば、成功体験を持たない失敗者たちからの支持を得られ易い。この「実力も運のうち」というキャッチコピーを真に受けた支持者たちは、嫉妬で他人の成功から学習できなくなり、自分の意思決定の過ちを反省することすらできなくなる。そうして失敗者のままに留まる支持者が増えれば、「実力も運のうち」というキャッチコピーを流布するビジネス哲学も「マッチポンプ的に」儲かり続けることになる。だから、都合が良い訳だ。
「能力主義」は、近代公教育の選抜制度や企業の人事制度で導入されるために、主に「教育(Erziehung, education)」の問題として認識される傾向にある。それ故、「能力主義」への批判は、主に現行教育制度に対する批判を意味する。教育を「社会批判のツール」として扱う教育学者や社会運動家たちの主張に耳を傾けるなら、まさに「教育」そのものが、「格差社会」や「資本主義」に対する「批判的な」意識を先鋭化させるための「興奮剤」となっていることがわかる。この意味では、「実力も運のうち」というビジネス哲学のキャッチコピーの内容も、それを屁理屈として応用する者たちの主張も、実はさして新しい指摘ではない。
これを前提に類推するなら、「教育」にもまた、「失敗者を失敗者のままにしておく機能」が備わっていることがわかる。現行教育制度に対する「批判的な」意識もまた、成功体験を持たない失敗者たちからの支持を得られ易い。学校の「改革」を主張する運動もまた、ビジネスに活かせば、「マッチポンプ的に」儲かり続ける可能性がある。
同様の類推から、教育批判や学校改革論の逆機能も推論することができる。それは、他者の成功体験から学習する機会が、喪われないまでも、軽視される危険があるという逆機能だ。この逆機能は、人生や社会に絶望しておらず、これから成功に向けて挑戦しようとする者にとっては、枷である。
この枷を取り払うには、教育理論に「鎮静剤」を打たなければならない。
本書は、この興奮した教育理論の鎮静化を目指す過程で、IT業界の教育理論を主題としている。いわゆる「成人学習」、「社内研修」、「プログラミングスクール」、「メンター制度」などのように、IT企業の人材開発に資する教育理論が、本書の主題となる。
「教育」の制度やカリキュラムを設計する時、自分が受けたことのある「教育」だけを手掛かりにする教育者は、そう多くないはずだ。成人教育にせよ、社内研修にせよ、あるいは「プログラミングスクール」にせよ、自分が受けた義務教育や大学の講義ばかりを参考にしたところで、学習者のためになる教育は実現しない。
オットー・フォン・ビスマルクを引き合いに出すまでもなく、自分の「経験(Erfahrungen)」から学ぶことができると信じているのは、愚者だけである。本書は、実際にお会いしたことのある教育者たちよりも、賢者を見習い、歴史から学ぶ姿勢を貫いている。
近代公教育の歴史を俯瞰するなら、それが失敗の歴史であったことは直ぐにわかる。子供を対象とする義務教育で生じていたこの失敗の歴史は、成人教育や生涯学習の文脈でも繰り返されている。こうした教育の歴史に対して「批判的な」眼差しを向けていた教育論者たちも少なくはなかったが、その活動が実ることは無かった。その「批判的な」意識は、資本主義経済や国家、ついには近代社会に向いたままであり、教育それ自体の問題は度外視されている。
教育学の大半は、教育とは「社会批判のツール」であるという「批判的な」意識を満足させるために、多くの年月を費やしてきた。しかし残念なことに、「能力主義」や「格差社会」への批判で忙しい学者たちがその片手間で書いた教育理論には、参考になる情報がほとんど見当たらない。企業内研究開発の「実学」に役立つ教育理論が見当たらない以上は、自分で記述するしかないであろう。教育を主題としている本書の概念実証は、この穴埋めを目指して取り組まれている。
シリーズ一覧
- 同シリーズの電子書籍はありませんでした。
この期間中は料金が980円→0円となるため、この記事で紹介している電子書籍は、すべてこのKindle Unlimited無料体験で読むことが可能です。