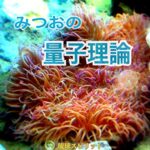著者:やすい ゆたか
ページ数:261
¥500 → ¥0
『中国思想の長征』は『第三巻、宋・明・清の思想をたどる』に入ります。現在中国では国学といって中国の古典典籍を学ぶ人が増えているそうです。中国は今後ますます経済発展を遂げ世界随一の超大国に発展する勢いですが、他方で地域格差や階層間の所得格差、環境破壊なども深刻になっており、長期的ビジョンにたった国づくりの方向を見定めなければ成りません。
改革開放政策の成功は世界経済のグローバル化に伴うものですから、グローバル化を前提にした世界にも受け入れられる方向性も持たなければならないわけです。そしてそれができるのは中国自身に内在的にそういう潜在的な可能性があるからです。そういう意味で中国三千年の歴史を総括し、中国自身の思想の発展として二十一世紀の中国現代思想を展望する必要があります。
その際やはり中国思想史からどんな傾向を今後の思想の重要な要素になりそうなものとして評価できるかということですね。
改革と言えば宋代の王安石の新政が思い起こされます。彼は飽くまでも孔孟の精神に立ち戻って、仁義に基づく王道政治を行おうとしたわけです。ですから貧農や貧民にとって仕事がやりやすくなり、暮らしやすくなる改革でした。改革開放を推進した鄧小平の実事求是は、ますます重みを持つでしょう。それは当然功利性や合理主義を伴います。でも成長や利益を求めるあまり格差拡大のひずみや環境破壊を伴いました。
中国や日本が本当にみんなが豊かで幸福な国になるためには王安石の新政から学び取るべきものが有ると思われます。つまり低所得者にこそ教育や福祉を充実させ、所得を配分して、様々な学習、スポーツ、社会活動などに参加して自己実現の機会を与え、それによって社会や経済を活性化するということです。
南宋では朱熹の朱子学の形成が特筆されます。宋は金によって一一二六年靖(せい)康(こう)の変で滅ぼされ、南に逃れた人たちが南宋を作りました。金(きん)に貢がされながらも、いつの日か尊王攘夷で領土を取り戻そうと、節約して富国強兵に励もうということですね。そのためには身を慎んで理を窮める「居敬窮理」をモットーに、厳粛主義の学問体系として朱子学が形成されたのです。時代の危機を背負って自覚的に生きる魂なしには、新たな時代は切り開けないわけで、二十一世紀のグローバル社会を牽引しようとする中国にとって、朱熹の私利私欲に惑わされないで学問の原点に立ち返ることはますます求められていると言えるでしょう。
朱熹は人間の本性は理だとしてそれが欲情によって濁らないように、性と情を峻別したわけですが、心は性と情とに分けられない、情の無い理知というのは感情が伴わないひからびたものになってしまうとして、心即理を唱えたのが陸象山(りくしょうざん)です。その教えを明代に陽明学(ようめいがく)として大成したのが王陽明(おうようめい)です。心即理は人間の心がそのまま対象である物の現れであるとし、「万物一体の仁」と呼ばれました。実はこれは本居宣長の「もののあはれ」に連なっていくわけで、日本思想を知る上でも王陽明は大切です。それは知ること感じることと行動することが表裏一体になっているアツアツの知のあり方を示していて、我々が二十一世紀の問題に取り組む際にも、我々の知は熱い血がたぎっているか問いかけてきます。
陽明学が本居宣長や吉田松陰に届いたのは実は李卓吾(りたくご)を介してではないかと思われます。彼は朱子学の教養を科挙試験で書く八股文(はっこぶん)の達人で、朱子学はもはや受験用の模範解答の意味しかなく、生きた学問ではないということを骨身に沁みていました。そしてまっさらな童心(どうしん)に戻って心の命ずるママに行動することの大切さを文芸批評などによって語り、大いに人気を博したのですが、当局に睨まれて七十六歳で収監され獄中で自殺しました。
官と切れて市井の独居人として言論界に生きる李卓吾は、はたして時代の寵児(ちょうじ)だったか徒(あだ)花(ばな)にすぎなかったかとても興味が惹かれます。
1840~42年のアヘン戦争で清国は大英帝国の理不尽な要求をのまされました。欧米列強の植民地化の屈辱的な歩みが強まったのです。でも人民の怒りは、悪辣な大英帝国に対してよりも、むしろ弱体を晒した清国に対して向けられたのです。洪秀全(こうしゅうぜん)は科挙の試験に三度も落第して寝込んでしまい、
夢で上帝から神の子として地上を支配することを命じられます。しかもこの上帝をキリスト教のエホバと同一視し、太平天国を建国して清国を打倒し、将来的には世界を支配しようという幻想を抱くわけです。
この運動は土地を天王である洪秀全に一元化し、みんなが豊かになるように運用するという大同思想に基づくユートピアを目指しました。それで貧農や貧民には熱烈に歓迎されたものの、地主や資産階級には反撥されたのです。
一時は南京を天京として清国を脅かしましたが、内部の権力闘争が苛烈になったこともあり、制圧されてしまったのです。
清国に対抗するためにキリスト教の中国化をはかったこと、変革の論理として、大同思想を復権させたこと、高い倫理性と美意識で太平天国軍を統率したことなどは驚嘆すべきですが、残念なことに、洪秀全の登場には歴史的な必然性は感じられますが、正気だったとは言い切れない面が残りますね。
太平天国の乱を鎮めた清国は、いかに富国強兵を実現して、欧米列強の植民地に凋落するのを防ぐかに全力で取り組まなければなりません。しかしその際に、清国の皇帝独裁の王朝体制を否定して、欧米近代の政治制度に脱皮しようというのではなかったのです。そうではなくて悠久の皇帝独裁の王朝体制を守りつつ、欧米列強から進んだ科学技術、産業システムを取り入れるということです。それを「中体西用(ちゅうたいせいよう)論」と呼びました。この考えに基づいて欧米の技術や資本をとりこんで近代的な工場が作られていきました。その動きを洋務(ようむ)運動とよびます。曽国藩(そうこくはん)、李鴻章(りこうしょう)、張子洞(ちょうしどう)らが活躍したのです。
この洋務運動は、欧米の技術や資本で富国強兵を図り、植民地化を防止しようとしたのですが、そのためには日本との近代化競争に勝たなければなりませんでした。日清戦争の敗北で、洋務運動は挫折したのです。
殖産興業、富国強兵で遅れをとってしまったのは、やはり改革や近代化を妨げる旧勢力が実権を握っているからです。下関条約を破棄して徹底抗戦すべきだと『公車上書(こうしゃじょうしょ)』を提出した康有為(こうゆうい)らは、西太后(せいたいこう)一派をしりぞけ、光緒帝(こうしょてい)をもり立てて改革を実行するための「戊戌政変(ぼじゅつせいへん)」を企てましたが、袁世凱(えんせいがい)に裏切られて失敗しました。この康有為らの運動を「変法自彊(へんぽうじきょう)運動」といいます。彼らも理想は大同思想です。ユートピアをめざしているのですが、段階論としては立憲君主制を目指し、欧米の科学技術と資本を取り入れて近代化を図ろうとするものです。
もちろん中国が心を一つにして近代化に取り組み、欧米列強の植民地状態を脱却するには、少数の満州族による王朝支配体制を打破する必要があります。それは第四巻でとりあげます。
改革開放政策の成功は世界経済のグローバル化に伴うものですから、グローバル化を前提にした世界にも受け入れられる方向性も持たなければならないわけです。そしてそれができるのは中国自身に内在的にそういう潜在的な可能性があるからです。そういう意味で中国三千年の歴史を総括し、中国自身の思想の発展として二十一世紀の中国現代思想を展望する必要があります。
その際やはり中国思想史からどんな傾向を今後の思想の重要な要素になりそうなものとして評価できるかということですね。
改革と言えば宋代の王安石の新政が思い起こされます。彼は飽くまでも孔孟の精神に立ち戻って、仁義に基づく王道政治を行おうとしたわけです。ですから貧農や貧民にとって仕事がやりやすくなり、暮らしやすくなる改革でした。改革開放を推進した鄧小平の実事求是は、ますます重みを持つでしょう。それは当然功利性や合理主義を伴います。でも成長や利益を求めるあまり格差拡大のひずみや環境破壊を伴いました。
中国や日本が本当にみんなが豊かで幸福な国になるためには王安石の新政から学び取るべきものが有ると思われます。つまり低所得者にこそ教育や福祉を充実させ、所得を配分して、様々な学習、スポーツ、社会活動などに参加して自己実現の機会を与え、それによって社会や経済を活性化するということです。
南宋では朱熹の朱子学の形成が特筆されます。宋は金によって一一二六年靖(せい)康(こう)の変で滅ぼされ、南に逃れた人たちが南宋を作りました。金(きん)に貢がされながらも、いつの日か尊王攘夷で領土を取り戻そうと、節約して富国強兵に励もうということですね。そのためには身を慎んで理を窮める「居敬窮理」をモットーに、厳粛主義の学問体系として朱子学が形成されたのです。時代の危機を背負って自覚的に生きる魂なしには、新たな時代は切り開けないわけで、二十一世紀のグローバル社会を牽引しようとする中国にとって、朱熹の私利私欲に惑わされないで学問の原点に立ち返ることはますます求められていると言えるでしょう。
朱熹は人間の本性は理だとしてそれが欲情によって濁らないように、性と情を峻別したわけですが、心は性と情とに分けられない、情の無い理知というのは感情が伴わないひからびたものになってしまうとして、心即理を唱えたのが陸象山(りくしょうざん)です。その教えを明代に陽明学(ようめいがく)として大成したのが王陽明(おうようめい)です。心即理は人間の心がそのまま対象である物の現れであるとし、「万物一体の仁」と呼ばれました。実はこれは本居宣長の「もののあはれ」に連なっていくわけで、日本思想を知る上でも王陽明は大切です。それは知ること感じることと行動することが表裏一体になっているアツアツの知のあり方を示していて、我々が二十一世紀の問題に取り組む際にも、我々の知は熱い血がたぎっているか問いかけてきます。
陽明学が本居宣長や吉田松陰に届いたのは実は李卓吾(りたくご)を介してではないかと思われます。彼は朱子学の教養を科挙試験で書く八股文(はっこぶん)の達人で、朱子学はもはや受験用の模範解答の意味しかなく、生きた学問ではないということを骨身に沁みていました。そしてまっさらな童心(どうしん)に戻って心の命ずるママに行動することの大切さを文芸批評などによって語り、大いに人気を博したのですが、当局に睨まれて七十六歳で収監され獄中で自殺しました。
官と切れて市井の独居人として言論界に生きる李卓吾は、はたして時代の寵児(ちょうじ)だったか徒(あだ)花(ばな)にすぎなかったかとても興味が惹かれます。
1840~42年のアヘン戦争で清国は大英帝国の理不尽な要求をのまされました。欧米列強の植民地化の屈辱的な歩みが強まったのです。でも人民の怒りは、悪辣な大英帝国に対してよりも、むしろ弱体を晒した清国に対して向けられたのです。洪秀全(こうしゅうぜん)は科挙の試験に三度も落第して寝込んでしまい、
夢で上帝から神の子として地上を支配することを命じられます。しかもこの上帝をキリスト教のエホバと同一視し、太平天国を建国して清国を打倒し、将来的には世界を支配しようという幻想を抱くわけです。
この運動は土地を天王である洪秀全に一元化し、みんなが豊かになるように運用するという大同思想に基づくユートピアを目指しました。それで貧農や貧民には熱烈に歓迎されたものの、地主や資産階級には反撥されたのです。
一時は南京を天京として清国を脅かしましたが、内部の権力闘争が苛烈になったこともあり、制圧されてしまったのです。
清国に対抗するためにキリスト教の中国化をはかったこと、変革の論理として、大同思想を復権させたこと、高い倫理性と美意識で太平天国軍を統率したことなどは驚嘆すべきですが、残念なことに、洪秀全の登場には歴史的な必然性は感じられますが、正気だったとは言い切れない面が残りますね。
太平天国の乱を鎮めた清国は、いかに富国強兵を実現して、欧米列強の植民地に凋落するのを防ぐかに全力で取り組まなければなりません。しかしその際に、清国の皇帝独裁の王朝体制を否定して、欧米近代の政治制度に脱皮しようというのではなかったのです。そうではなくて悠久の皇帝独裁の王朝体制を守りつつ、欧米列強から進んだ科学技術、産業システムを取り入れるということです。それを「中体西用(ちゅうたいせいよう)論」と呼びました。この考えに基づいて欧米の技術や資本をとりこんで近代的な工場が作られていきました。その動きを洋務(ようむ)運動とよびます。曽国藩(そうこくはん)、李鴻章(りこうしょう)、張子洞(ちょうしどう)らが活躍したのです。
この洋務運動は、欧米の技術や資本で富国強兵を図り、植民地化を防止しようとしたのですが、そのためには日本との近代化競争に勝たなければなりませんでした。日清戦争の敗北で、洋務運動は挫折したのです。
殖産興業、富国強兵で遅れをとってしまったのは、やはり改革や近代化を妨げる旧勢力が実権を握っているからです。下関条約を破棄して徹底抗戦すべきだと『公車上書(こうしゃじょうしょ)』を提出した康有為(こうゆうい)らは、西太后(せいたいこう)一派をしりぞけ、光緒帝(こうしょてい)をもり立てて改革を実行するための「戊戌政変(ぼじゅつせいへん)」を企てましたが、袁世凱(えんせいがい)に裏切られて失敗しました。この康有為らの運動を「変法自彊(へんぽうじきょう)運動」といいます。彼らも理想は大同思想です。ユートピアをめざしているのですが、段階論としては立憲君主制を目指し、欧米の科学技術と資本を取り入れて近代化を図ろうとするものです。
もちろん中国が心を一つにして近代化に取り組み、欧米列強の植民地状態を脱却するには、少数の満州族による王朝支配体制を打破する必要があります。それは第四巻でとりあげます。
シリーズ一覧
- 同シリーズの電子書籍はありませんでした。
Kindle Unlimitedは、現在30日間無料体験キャンペーンを行っています!
この期間中は料金が980円→0円となるため、この記事で紹介している電子書籍は、すべてこのKindle Unlimited無料体験で読むことが可能です。